春風亭昇太の愛車はなに?
春風亭昇太さんといえば落語家というイメージが強いですよね。
でも実は、昭和の車にも詳しいんです!
昇太さんの車歴を見ると、まるで昭和の名車図鑑みたい。
1991年にはローバー ミニ、1995年にはトヨタ パブリカ 800、そして1997年にはダットサン ブルーバード。
どれも昭和を感じさせる車ばかりです。

出典:ENGINE
でも、その中でも特別な存在が1967年式のトヨタ・パブリカです。
なんとこの愛車、24年間も大切に乗り続けているんです。
800ccという今どきからすると小さなエンジンと、2段ATという珍しいトランスミッション。
現代の車とはちょっと違う、レトロな魅力がいっぱいつまった車なんですね。
春風亭昇太さんは「休日にこの車で街をぶらっと走るのが最高の息抜きなんだ」とのこと。
昭和歌謡を流しながらのドライブ。まるでタイムスリップしたみたい。
私も一度乗ってみたいな~。
24年間も故障知らずで走り続けているのって、すごくないですか?
これって、春風亭昇太さんの丁寧なメンテナンスあってこそなんです。
キャブレターの調整や電気系統のチェックなど、昔の車ならではの手入れを欠かさないんです。
「昭和の車って、メンテナンスが必要不可欠なんだよね」と春風亭昇太さん。
でも、その手間が逆に楽しみになっているみたい。
自分の手で車を大切にする。その過程で愛着が深まっていくんでしょうね。
私も何か大切にできるものを見つけなきゃなあ。
「昭和の車は、幸せだった子供の頃を思い出させてくれるんだ」
という春風亭昇太さん。
私は、春風亭昇太さんの愛車への思いを聞いていると、車って単なる移動手段以上の存在なんだなって感じます。
趣味や生活の一部として、愛着を持って付き合う。
そんな車との関係性を見ていると、私たちが日々使っているものにも、もっと愛情を注げるんじゃないかなって思うんです。
例えば、毎日使っているスマホだって、ちょっとしたカスタマイズや丁寧な扱いで、もっと愛着のわく存在になるかもしれない。
春風亭昇太さんの姿勢は、現代の私たちにも通じる、モノとの付き合い方の本質を教えてくれているような気がします。
春風亭昇太はトロンボーン奏者?
春風亭昇太さんがトロンボーンを始めたきっかけには、師匠である5代目春風亭柳昇(しゅんぷうていりゅうしょう)さんの存在がありました。

出典:日刊ゲンダイDIGITAL
柳昇さんもトロンボーンを演奏しており、春風亭昇太さんは師匠のトロンボーンを引き継いで使っているんです。
楽器を通じて師弟の絆が深まる様子は、伝統芸能の世界ならではの美しさを感じさせます。
春風亭昇太さんは「にゅうおいらんず」というバンドで演奏しています。
このバンドは落語家たちで結成されたデキシーランドジャズバンド(20世紀初頭にアメリカ南部で発展した、集団即興演奏が特徴的なジャズスタイル)で、リーダーは三遊亭小遊三さんです。
しかし、落語家としての活動とバンド活動の両立は簡単ではありません。
春風亭昇太さんは「笑点」の収録、落語の公演、そしてバンドの演奏と、多忙なスケジュールをこなしています。
時には舞台公演と「笑点」の収録が重なることもあるそうですが、他のメンバーと相談しながら調整しているとのことです。
私は、落語とジャズの融合に、意外にも多くの共通点があるように感じます。 どちらも即興性があり、観客とのやり取りを大切にします。 春風亭昇太さんがこの二つの世界で活躍しているのも、納得できる気がします。
機会があれば、春風亭昇太さんのトロンボーン演奏を聴いてみたいです。
きっと、いつもとは違う春風亭昇太さんの魅力があるはず。
落語とジャズ、二つの世界を行き来する春風亭昇太さんの姿を見ていると、一つのことに縛られず、好きなことを思い切り楽しむ生き方っていいな、って思えてきます。
年齢を重ねても新しいことに挑戦し続ける姿勢がすごいです。
落語とジャズ、一見かけ離れた二つの世界を行き来する春風亭昇太さん。
でも、よく考えてみると、どちらも「その場の空気を読む力」が必要な芸能ですよね。
春風亭昇太さんの中では、この二つがごく自然につながっているのかもしれません。
私たちの中にも、一見バラバラに見える興味や経験が、実は深いところでつながっているのかも。
例えば、学生時代に打ち込んだ部活動での経験が、今の仕事に活きていたり。
あるいは、趣味で始めた料理が、家族との絆を深めるきっかけになっていたり。
人生の様々な出来事や興味が、実は無駄なく自分を形作っているんだなって、春風亭昇太さんの活躍を見ていると気づかされます。
春風亭昇太と城郭!!(そもそも城郭とは?!)
城郭とは、城(または町)を敵の攻撃から守るための施設のことを言います。
春風亭昇太さん、城郭が大好きなんです。

出典:婦人公論
お城といえば、白くてそびえ立つ天守閣をイメージしますよね。
でも、春風亭昇太さんが夢中になっているのは、ちょっと違うんです。
なんと、夢中になってるのは中世の山城なんですよ!
山城って何?って思いますよね。
簡単に言うと、山の地形を利用して作られた城のことなんです。
平地に建つお城と違って、山の斜面や頂上に築かれていて、自然の地形を巧みに使って防御しやすくしているんです。
天守閣はないけど、土塁(どるい)や堀切(ほりきり)といった防御施設があるのが特徴です。
どうして山城に夢中なのかって?
それは山城の「地域性」と「多様性」にあるんだとか。
平地のお城が全国的に同じような造りなのに対して、山城は地域ごとの地形や文化によって、それぞれ個性豊かな特徴を持っているんです。
まるで、各地の方言みたいですね。
春風亭昇太さんの城めぐりは、地元の江尻城(えじりじょう)との出会いから始まりました。
中学生の時に知ったこの城は、平地に築かれた平城(ひらじろ)でした。
平城は、その名の通り平地に築かれたお城のこと。
でも、この出会いが春風亭昇太さんを山城の世界へと導いていくんです。
特に衝撃を受けたのが、静岡県の庵原山城(いはらやまじろ)との出会い。
初めて目にした堀切(ほりきり)に驚いたそうです。
堀切って聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単に言うと、山の尾根を人工的に切り取って作った深い溝のこと。
これが城の防御に使われていたんです。
「こんなすごいものを、あの時代の人々が作ったんだ!」という感動が、春風亭翔太さんの心をガッチリ掴んだんでしょうね。
春風亭昇太さん、すごいんです。
年間約40か所もの城を訪れて、これまでに約600の城を巡っているんです!
私なんて、年に一度の旅行の計画を立てるのに四苦八苦しているのに、本当に頭が下がります。
そんな春風亭昇太さんのお気に入りの城は、富山県砺波市(となみし)の増山城跡(ますやまじょうあと)なんです。
なんでも「城主になりたい山城」の1位に選んでいて、名誉城主にも認定されているんですよ。
名誉城主って、その城跡の保存や PR に貢献した人に与えられる称号なんです。
つまり、春風亭昇太さんの城への愛情と熱意が富山県砺波市に認められたってことですね!
切岸(人工的な急斜面)を見て、「この城の防御力はスゴイ!」と興奮気味に語る春風亭昇太さんの姿を想像すると、思わず笑みがこぼれちゃいます。
面白いのは、この趣味が仕事にも活かされていることです。
春風亭昇太さんは、地方での落語会の際に近くの城跡を訪ねて、その体験を落語の枕(まくら)として使います。
「今日、○○城へ行ってきました」なんて話を始めると、観客との距離がグッと縮まるんだとか。
春風亭昇太さんは城めぐりのコツも教えてくれています。
・事前に城の歴史を調べておくこと
・地元の文化や食べ物を楽しむこと
・安全には十分注意すること。
特に山城では滑落やスズメバチに気をつけるそうです。
春風亭昇太さんの城への愛着を見ていると、趣味って本当に人生を豊かにするんだなって感じます。
テレビで見る姿とはまた違う、熱中する春風亭昇太さんの姿、想像するとちょっとかわいいと思うのは私だけ?
昇太さんは、本当に歴史が好きなんですね、大学も文学部史学科でしたし。
春風亭昇太の缶詰への熱い思いとは?
春風亭昇太さんの趣味といえば、お城めぐりが有名です。
でも、実はもう一つ、意外な趣味があるんです。
それは、なんと缶詰集め!

出典:みんなのきょうの料理
きっかけは、春風亭昇太さんの生まれ育った静岡県清水市(現・静岡市清水区)にあります。
この地域は「缶詰王国」として知られています。
日本で初めてまぐろ油漬缶詰を作ったのが清水市でした。
春風亭昇太さんは、缶詰のことを「すごいねー。缶詰にできないものはない!」と語ります。
その多様性と可能性に感銘を受けているようです。
驚くべきことに、春風亭昇太さんの自宅には400個以上の缶詰が常備されています。
まさに缶詰コレクターですね!
春風亭昇太さんの缶詰愛は、幼少期の温かい思い出に深く結びついています。
特に心に残っているのが、お父さんが缶詰を開けて、ご飯の上に載せてくれた時のこと。
その頃の家庭では、お父さんだけに特別なおかずが出ることがあったんです。
その特別なおかずは、時にはお刺身だったり、また時には缶詰だったりしました。
そんな「特別」な扱いを受けていた缶詰を、お父さんが昇太さんのご飯にもそっと載せてくれたんですね。
家族の中でちょっと特別な存在だったお父さんと、缶詰。
この温かくて少し特別な記憶が、缶詰への愛着をより一層深めたのでしょう。
春風亭昇太さんのお気に入りの缶詰には、いくつか種類があります。
特にホテイフーズの焼き鳥缶が好きなのです。
この焼き鳥缶を使って、簡単に親子丼を作れます。
手軽さと美味しさを両立できるなんて、さすが缶詰です。
きっと、子供の頃に感じた「特別感」も、この手軽さの中に見出しているのかもしれませんね。
缶詰と言えば保存食のイメージが強いですが、春風亭昇太さんはそれ以上の価値を見出しています。
例えば、サバの味噌煮缶については「下手な店よりも美味しい」と絶賛。
その上、価格の手頃さにも驚いています。
缶詰への愛は料理にも活かされています。
春風亭昇太さんお気に入りのレシピをいくつか紹介しましょう。
焼き鳥缶を使った親子丼:
生卵の黄身と白身を分け、白身を泡立ててメレンゲを作ります。
これをご飯の上に乗せ、焼き鳥缶をそのまま載せ、最後に黄身とネギをトッピング。
なんと、わずか1分57秒で完成します!
サバ缶とネギのバター焼き:
サバ缶を缶汁ごと耐熱容器に入れ、たっぷりのネギを載せます。
中央にバターを適量トッピングし、オーブンで約5分間加熱。
最後にしょうゆをたらして完成です。
オーブンの加熱時間を含めても6分17秒でできあがります。
春風亭昇太さんの缶詰愛を見ていると、身近なものの中に驚きや喜びを見出す大切さを忘れてないことが分かります。
テレビで見る姿からは想像もつかない、缶詰マニアとしての一面。
もう、私だけでしょうか、とても春風亭昇太さんの隠れた魅力にやられちゃってます(笑)
かっこいいですよね、春風亭昇太さんの生き方。
春風亭昇太の趣味のまとめ
春風亭昇太さんの趣味の世界、いかがでしたか?
テレビでおなじみの落語家さんの意外な一面を知ると、なんだかぐっと親近感が湧いてきますよね。
ここで、昇太さんの趣味についておさらいしてみましょう。
・愛車:1967年式のトヨタ・パブリカを24年間愛用。
・トロンボーン演奏:バンド「にゅうおいらんず」のメンバーとして活躍。
・お城めぐり:特に中世の山城に魅了され、年間約40か所訪問。
・缶詰コレクション:自宅に400個以上の缶詰を常備。
これらの趣味を通じて見えてくるのは、春風亭昇太さんの好奇心旺盛な性格と物事を深く追求する姿勢です。
単に趣味として楽しむだけでなく、その知識や経験を落語や話芸に活かしています。
春風亭昇太さんの趣味には、ある共通点があります。
それは、“古いもの”への愛着です。
昭和の車、伝統的な楽器のトロンボーン、中世の山城、そして缶詰。
これらはみな、ある意味で「古い」ものです。
でも春風亭昇太さんは、それらを単に「懐かしい」で終わらせていません。
むしろ、現代の生活に溶け込ませ、新しい価値を見出しています。
古い車でドライブを楽しみ、トロンボーンでジャズを演奏し、山城の魅力を多くの人に伝え、
缶詰で手軽な料理を考案する。
この「古いものを現代に活かす」姿勢。
これこそが、春風亭昇太さんの趣味の本質なのかもしれません。
多才な顔を持っている春風亭昇太は、学生時代はどのような人だったのでしょうか。
昇太さんの学歴については、こちらでご紹介しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


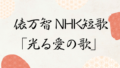
コメント